
2025年夏に開催予定の全国の夏休みイベント&おでかけスポットがエリア別に探せる!
夏祭りなどのイベントや、プール、海水浴場、BBQ・キャンプ場など、遊べるスポットを大紹介!
ホラー体験型展覧会「1999展 ―存在しないあの日の記憶―」をレポート!『近畿地方のある場所について』原作者や『SIREN』脚本家らが手掛ける異色展
東京都
東京・六本木ミュージアムにて、「世界の終わり」をテーマにしたホラー体験型の展覧会「1999展 ―存在しないあの日の記憶―」が2025年7月11日から9月27日(土)まで開催中だ。

本展を企画したのは実写映画の公開も近づく『近畿地方のある場所について』の原作者・背筋さん、ホラーゲーム「SIREN」をはじめさまざまな作品を手掛ける脚本家の佐藤直子さん、若手ホラー映画監督の西山将貴さんの3人からなるホラークリエイターユニット「バミューダ3」。1999と世界の終わりという2つのキーワードからわかるように、ノストラダムスの大予言の「もしも」を体感できる内容で、イラストレーターの米山舞さんが描いた“終末の少女”に導かれながら、展覧会の物語を感じとるという異色のコンセプトとなっている。

ウォーカープラスはメディア向け内覧会に参加し、その見どころをレポート。また、バミューダ3の3名による質疑応答の模様もお届けする。
物語は自分で作り上げる。異色の展覧会への挑み方

率直に言えば、本展をどう紹介すべきかは戸惑った。というのも、ホラー体験型と言えどもあくまで「展覧会」であり、お化け屋敷やリアル謎解きゲームのようなアトラクションでは決してないからだ。その一方で、展覧会のディティールを語りすぎれば「ネタバレ」となってしまう。ノストラダムスの予言の年とされた1999年当時、初代プレイステーションやドリームキャストなどの家庭用ゲーム機ソフトに数多く現れた、3DCGの世界を少ないヒントでさまよい読み解いていくような感覚が本展にはあり、佐藤さんの「歩ける舞台、ゲームで言うとウォーキングシミュレーターと呼ばれるようなジャンル」という説明にも肯けた。


また、「存在しないあの日の記憶」のタイトル通り、世界の滅びが表現された展示内容は不穏さや不可解さに満ちている。しかし、ホラーコンテンツに定番のジャンプスケア演出、いきなり驚かせるというようなことはほぼ皆無なので、苦手な人でもその点は安心してほしい。ただし、ホラーテイストの雰囲気そのものがとても苦手という場合、多少は心の準備が必要になるだろう。

ツアー冒頭で佐藤さんが「さまよう人々の声に耳を傾けてはじめて、みなさま自身が物語を発見できる構成となっています」と語ったように、本展の展示やその構成には、一貫したストーリー性があるように感じられる。一方で、最後の展示ではっきりとした結末が明かされることはない。それぞれの展示を見聞きし、考えそして感じ取って、自分なりの解釈やインスピレーションを得るという点では、やはり美術館や博物館で催される展覧会と同様のスタイルだ。
展覧会は大きく8つのエリアに分かれており、最初のエリアでは1999年、とある男の部屋が再現されている。筆者は99年当時すでに10代だったが、世紀末と呼ばれたころの生活感や雰囲気が忠実に表現され、懐かしさを感じる。当時を知らない世代からすれば、“平成レトロ”のような情景に映るだろう。
だが、その現実味はエリアを進むごとにぼやけていく。ブラウン管テレビに映し出されるニュース映像はだんだんと様子がおかしくなり、どの路線かも定かではない鉄道に乗り込むと、無人のはずの車両に誰かのつぶやきが響き、車窓越しに見える風景もめまぐるしく変化していく。


一般的な展覧会とは異なり、作品のかたわらにキャプションが添えられてはいないので、一体何が起き、自分はこの先どこに進んでいくのか、すべてが手探りだ。筆者は展示を巡る中で「胎内くぐり」というキーワードが思い浮かんだが、これはどこかに書かれていた内容ではなく、あくまで一つの感じ方に過ぎない。佐藤さんが「ぜひ立ち止まって、見えないさまよう人々の声に耳を澄ましてください」とツアー内で話したように、一つひとつの展示からヒントを拾い上げるつもりで巡るのをおすすめしたい。
なお、展示会場を出たあとにはグッズショップやカフェがあり、グッズのポップや喫茶店風のコラボメニュー、店内装飾にいたるまで展覧会と地続きの雰囲気がこめられているので立ち寄ってみてほしい。


バミューダ3の3人が語る、本展への思い
ツアー終了後は、バミューダ3の背筋さん、佐藤さん、西山さんがそろい、メディア向けの質疑応答が行われた。
背筋さんは「恐怖っていう感情を表現するときに、たとえば幽霊を出したりだとか、天国、地獄を出したりだとかは簡単だと思うんですが、そこに対しての感情はたぶん、皆さんおのおのお持ちだと思います。天国に対して憧れを持ったり、地獄に対して恐れを抱いたり。幽霊に関しても、単純に怖いお化けが出てきたら恐怖の対象になりますが、それが亡くなった肉親だったら、それは一気に救いになりえたりもすると思います。そういった目に見えないものに対しての感情みたいなものをあえて単純化せずに、複雑なままお出しすることで、皆さんにそれを咀嚼していただきたいというメッセージを込めて作らせていただきました。どうかその点を踏まえてお楽しみいただければ幸いです」とコメント。
展示会場全体の映像や、実写のキービジュアルポスターのディレクションを担当した西山さんは「僕自身、展示は一度もやったことなくて、ずっと映画を作って映画の監督をしてきたんですけど、だからこその映像に(1999展は)したいなと思っていて。特に前半のほうのエリアに出てくる電車の景色は、とても長い尺の映像を作っています。映画はカットがあるものを連続していくんですが、(展示映像では)来ていただいた方々に、体験としてその場にいるような、カットがないようなものにチャレンジしたいと。展示だからこそできるみたいなもので、すごく楽しくやらせていただきました。来てくださる方には映像にも注目して見ていただけたらうれしいです」と映像へのこだわりを語った。
そして佐藤さんは、展覧会の趣旨を「“世界の滅び”に一種の救いを求めたことがあるのではないかと思います。その究極の妄想の疑似体験、異界への訪問を通じて、“生きること”の再確認」と話し、本展の成り立ちについて舞台裏を明かす。
「私はずっとゲームを作っていて、今は独立してアニメの脚本などもやっていますが、背筋は基本は小説家、西山は映画監督。この3人が“バミューダ3”を名乗って遊んでいたところに『展覧会企画をやりませんか?』という話があり、ホラーアート展覧会とはなんぞや、というところから今回の企画にたどり着きました。もともとは9月ぐらいに行う予定だったんですけれど、(主催の)SMEさんから「7月に六本木ミュージアム(のスケジュール)が空く」と言われまして。(ノストラダムスの大予言にあった)“1999年7の月”を2025年の7の月にやるということは運命なのだと思い、2カ月会期を早め、この企画を進めました」
また、とあるエリアにスマートフォンなど「1999展」からは時代が外れるような展示があったことについては「パネルの下に『1999または2025』というノンブルのような西暦がありまして」と、佐藤さんはその仕掛けの一端を説明する。
「パラレルワールド的な考え方も実は内包しているんですね。実はいつでもこの瞬間、誰しもが本当は“世界の終わり”を体験しているかもしれない。ただ、自分たちは“そうじゃない世界”にスライドしながら今の人生を生きているんじゃないかというSF的な考えを内包して、1999年の魂、2025年の魂を混在させております」
「疑似科学的用語に『マンデラ効果』と呼ばれる疑似記憶の概念があるんですけど、たくさんの人がある共通の“偽の記憶”を持っていたりするんですね。(註:「2013年まで存命だった南アフリカのマンデラ元大統領が『1980年代に死亡した』という誤った記憶を不特定多数の人が持っていた、という現象に由来する)
実は並行世界が存在していて、その並行世界の記憶が混ざり込んで、そういう疑似記憶を所持している人たちがいるんじゃないか、というような説もあります。なので、ある意味、私たちも今“世界の終わり”という並行世界を体験し、今、元の世界に戻ってきた人格、魂なのかもしれないというものを裏設定で考えています」
この夏、世界の終わりを体験しにいこう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
この記事で紹介されたイベント・スポット
詳細情報
■1999展 ―存在しないあの日の記憶―会期:2025年7月11日~9月27日(土)
時間
日~木・祝:10:00~18:00
金・土・8月8日(金)~8月17日(日):10:00~20:00
※開館時間は変更の可能性あり、詳細は公式サイトをご確認ください。
会場:六本木ミュージアム(東京都港区六本木5-6-20)
展覧会公式サイト:https://1999-kioku.jp/
チケット販売サイト:https://eplus.jp/1999-kioku/
公式X(旧Twitter):https://x.com/1999_kioku
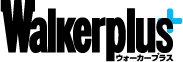
東京都の夏休みイベント・おでかけスポットを探す
| 夏休みの人気イベントランキング | 夏休みの人気スポットランキング |
都道府県から夏休みイベントを探す
夏休み特集2025
- 夏休みイベント
- 夏祭り
- 七夕祭り
- 縁日・納涼祭
- 盆踊り
- 屋台のある夏祭り
- 無料イベント
- 体験イベント・アクティビティ
- グルメ・フードフェス
- フリーマーケット
- コンサート・音楽イベント
- アニメ・ゲームイベント
- 花イベント
- 動物ふれあいイベント
- 美術展・博物展・展示会
- 演劇・講演会
- フェア
- 夏休みスポット
- キャンプ場・BBQ場
- グランピング
- 遊園地・テーマパーク
- 水族館・動物園
- プール
- ビーチ・海水浴場
- 温泉・スパリゾート
- アウトレット・ショッピングモール
- 商業施設・百貨店
- 工場見学
- 博物館・科学館
- 美術館
- 道の駅・SA/PA
- 公園
- アスレチック
- タワー・展望施設
- フードテーマパーク
- 牧場・レジャー&リゾート施設
おすすめ情報
閲覧履歴
-
最近見たイベント&スポットページはありません。
夏休みをもっと楽しむ
-
 2025年の涼しいイベント&グルメガイド夏の猛暑でもおでかけしたい!「涼」がテーマのおすすめ情報
2025年の涼しいイベント&グルメガイド夏の猛暑でもおでかけしたい!「涼」がテーマのおすすめ情報 -
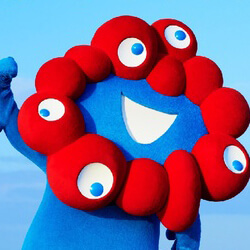 EXPO 2025 大阪・関西万博特集夏休みは万博へ出かけよう!お得な夜間券の紹介も
EXPO 2025 大阪・関西万博特集夏休みは万博へ出かけよう!お得な夜間券の紹介も -
 2025年の夏に行きたい七夕祭り13選!7月~8月にかけて開催される祭りを紹介
2025年の夏に行きたい七夕祭り13選!7月~8月にかけて開催される祭りを紹介 -
 夏休みにおすすめ!怖い漫画夏に読みたい怖い漫画をまとめてご紹介!
夏休みにおすすめ!怖い漫画夏に読みたい怖い漫画をまとめてご紹介! -
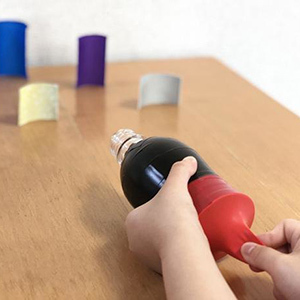 夏休みの工作のアイデア集学年別に夏休みの工作アイデアを紹介。無理なく無駄なく、自由工作に取り組もう!
夏休みの工作のアイデア集学年別に夏休みの工作アイデアを紹介。無理なく無駄なく、自由工作に取り組もう! -
 関東・関西の日帰り温泉関東や関西の日帰りできるおすすめの温泉をご紹介
関東・関西の日帰り温泉関東や関西の日帰りできるおすすめの温泉をご紹介 -
 2025年のお盆休みはいつからいつまで?最大9連休となる場合もあり
2025年のお盆休みはいつからいつまで?最大9連休となる場合もあり -
 2025年の夏休みはいつからいつまで?学校の夏休みを地域別にチェック!夏レジャーを計画しよう
2025年の夏休みはいつからいつまで?学校の夏休みを地域別にチェック!夏レジャーを計画しよう -
 夏休みイベントカレンダー日付から夏休みのイベントを探す
夏休みイベントカレンダー日付から夏休みのイベントを探す




